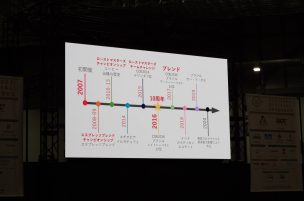
ローストマスターズチームチャレンジ
SCAJのお話の続き(最終回)です。
最終日の午後には焙煎のチーム戦「ローストマスターズチャンピオンシップ」が開催されました。
こちらは競技会というよりはワークショップ的な取り組みで、その目的も地域のロースターの交流や参加者(観客も含む)全員の技術向上だったりします。(私も2008年から10年間参加してずいぶん勉強させてもらいました)
チーム戦の流れとしては以下の通りです。
①全国から集まった焙煎人が数チームに分けられる
②チームごとに集まり配布された課題の生豆をテーマに沿って焙煎
③焙煎されたコーヒーはSCAJの会場にて抽出され、審査員や観客にふるまわれる
④審査員のカッピングや観客のテイスティングによる採点と投票によってそれぞれ「審査員特別賞」と「一般部門賞」の順位が決まる
⑤上位に入ったチームが焙煎の取り組みや焙煎工程を発表。それを会場にいる全員でシェア
年によっても少し違いますが、毎年だいたいこのような感じです。
今年のテーマは「深煎り」でした。深煎りは焙煎では避けては通れないテーマだと思いますが、実際にこのテーマが採用されたのは今回が初めてなんだそうです。意外ですね。(毎年議論はされてはいたようです)
そして初めてといえば、今回初めて「特別審査員賞」と「一般部門賞」を同じチームが取りました。
例年テーマは変われど、基本的には浅煎り一辺倒。そして「審査員特別賞」を取ったコーヒーは「一般部門」では勝てない、というジンクスのようなものがありました。
それは「生豆評価用のカッピングフォームで高い点数が付くコーヒーと一般の方が美味しいと思うコーヒーは必ずしも一致しない」という事を表しています。なぜそんな事になるのか。そこには何かしらの理由があるのでしょう。その辺りを考えてみるだけでも面白いです。
それが、今年深煎りになって初めて特別審査員と一般の方(会場にいるのが本当の「一般人」なのかどうかはさておき)の評価が一致した、というのは印象的でした。
今回審査する側として参加して、あらためて感じたのは「深煎りを`評価’すること」の難しさです。
スペシャルティコーヒーの評価フォームは最終的に「生豆の品質」に帰結するものなので、ある程度ゴールを決める事が出来るし、それを色々な価値観を持った人同士で共有することも可能です。
それに比べて深煎りの評価は本質的に「製品の良し悪し」を判断するという事に繋がります。最終製品の話になってくると店舗ごとにそれぞれ作りたい味わいがあり、使用目的や抽出条件等も異なるため共通のゴール設定が難しくなります。
今回一番となったコーヒーは焙煎による瑕疵がないのはもちろん、液体の質感やバランスも良く、私も含め周りの知り合いのロースター全員が票を入れていました。それぐらい素晴らしいカップでした。
ただそれも競技会が指定した「カッピング」や「フレンチプレス」といった浸漬式の抽出方法で入れられた、その時の液体の評価でしかありません。今回のフォーマットの中では抜けた良さを持っていましたが、個人的に「ドリップ(ネル)で入れたらこっちの方が面白いかも..」と思わせるコーヒーは他にありました。(そしてそのコーヒーは入選しなかったので焙煎の取り組みの発表も無し。「深煎りはドリップ派」の自分としては少し残念でした)
やはり深煎りは難しい。必ずどこかに「正解」はあると思いますが、それが一つとは限らない。つまる所、各ロースターが出したい深煎りの味、お客さんがおいしいと思ってくれる深煎りの味を追求していくしかない気がしています。
勉強会などで情報を共有しながら「良い深煎りとは」を探求するのも良いとは思いますが、その行きつく先に「深煎り用カッピングフォーム」のようなものが出来て、全員で同じゴールを目指していく、という事になるとしたら・・・どうなんでしょう。。
浅煎りの時に一部であった
「プロ受けは良いけど一般のお客さんは置いてけぼり」
みたいな状況が深煎りでも生まれない事を祈っています。
三日間を終えて

SCAJには開業した2008年から毎年通っていて、今年初めて何の役割もなくSCAJをゆっくりと見て回ることが出来ました。
競技会やセミナーがほとんど無かったのでもっと閑散としているかと思っていたのですが会場は思いのほか盛況で、1年以上止まっていた時計の針が動き出した感じがして嬉しく思いました。
またコロナになって業界の集まりもほどんど無くなっていたので、久しぶりに色んなコーヒーマンに会場で会って元気な姿を見れたのも嬉しかったです。







今までSCAJの事を「業界人の同窓会」と揶揄する声もありましたが、「あ、本当にこれって同窓会だったんだな」と思いました。
世の中が早く落ち着いて、来年はもっと多くの生産者やコーヒーマン、コーヒーファンの皆さんと会場で再会できる事を心から祈っております。








